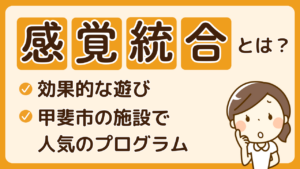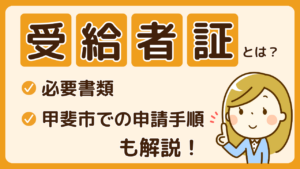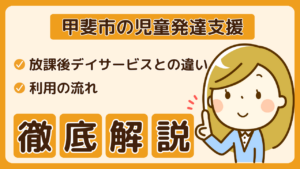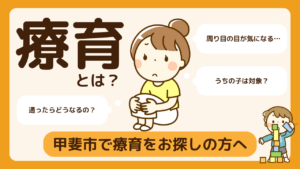【発達障害とは?】種類や特徴、甲斐市で受けられる支援についてもご紹介
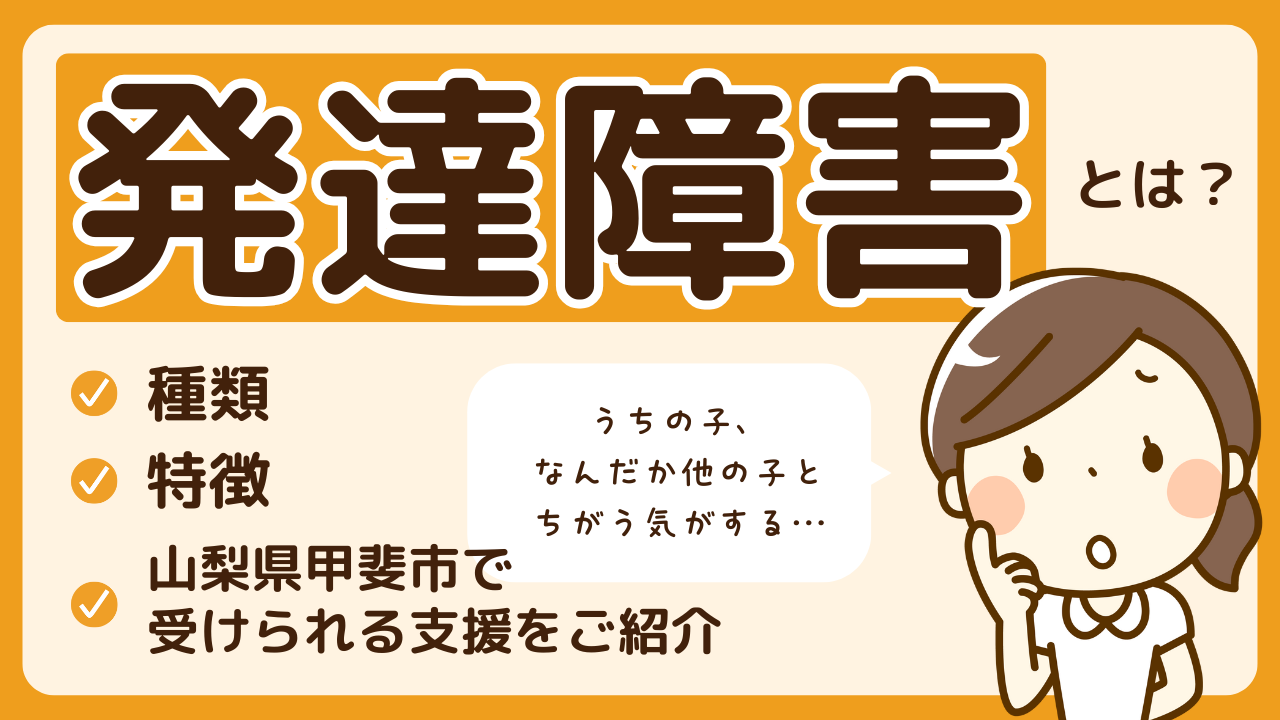
「うちの子、なんだか他の子と違う気がする」そんなふうに感じたことはありませんか?
お友だちとうまく遊べない。こだわりが強い。言葉がなかなか出ない。落ち着きがなくて目が離せない 。
子どもの成長に不安を感じても、「気のせいかも」と思ったり、「相談するほどのことじゃない」と迷ってしまったり。ひとりで悩みを抱えてしまうママは少なくありません。
この記事では、発達障害と何か、どんな特徴があるのか、そしてどこに相談すればよいのかなどについて、わかりやすくお伝えします。甲斐市で受けられる支援についてもご紹介するのでぜひ参考にしてみてください。
発達障害とは?
発達障害とは、生まれつきの脳の働き方の違いによって、行動や感情のコントロール、人との関わり方などに特性があらわれる状態のことです。特性のあらわれ方には個人差がありますが、日常生活や集団生活の中で何らかの困りごとを抱えているケースがほとんどです。
発達障害には、自閉スペクトラム症(ASD)・注意欠如・多動症(ADHD)・学習障害(LD)などの種類があり、同じ診断名でも症状や困りごとは一人ひとり異なります。さらに、知的な遅れがあるお子さんもいれば、そうでないお子さんもいます。
発達障害はママやパパの育て方が原因ではありません。しかし、関わり方しだいで、子どもが感じている生きづらさや困りごとを軽くすることも十分可能です。「発達障害児」と一括りにするのではなく、その子の特性を知り、寄り添った関わり方をすることが大切なのです。
発達障害の主な種類と特徴
発達障害にはいくつかの種類がありますが、ここでは代表的な3つをご紹介します。ひとつだけに当てはまる場合もあれば、いくつかの特性を併せ持っているお子さんもいます。
ASD(自閉症スペクトラム)
ASD(自閉スペクトラム症)は、人との関わり方や強いこだわりに特性が見られます。
相手の気持ちを想像するのが難しかったり、言葉のやりとりが一方通行になったりすることがあります。また、強いこだわりや、感覚の過敏さ・鈍さといった特徴もあります。
たとえば、いつもと違う順番で行動しただけで不安になったり、大きな音やまぶしい光、服の刺激を「つらい」「痛い」と感じるお子さんもいます。反対に、痛みに鈍感だったり、寒さをあまり感じなかったりすることもあります。
言葉の遅れや、集団行動への苦手などから、就園前後に特性に気づくことが多いでしょう。
【ASDの主な特徴】
- ひとり遊びが好き
- 相手の気持ちを読み取ることが苦手
- 会話がかみ合わない、独り言が多い
- 予定の変更が苦手で、こだわりが強い
- 感覚が過敏(音・光・触感など)または鈍感
- 特定の動きを繰り返す(手をひらひらさせる、回るものを見続けるなど)
- 癇癪を起す
ADHD(注意欠如・多動症)
ADHD(注意欠如・多動症)は、集中力が続かない・落ち着きがない、といった特性が見られます。
特性のあらわれ方にはタイプがあり、
- 「不注意」:話を最後まで聞けない・忘れ物が多い
- 「多動性」:じっとしていられない・おしゃべりが止まらない
- 「衝動性」:思いついたらすぐに行動してしまう
に分けられます。いずれかのタイプが強く出る子もいれば、全てのタイプが混在している子もいます。
ADHDの症状は、12歳より前からあらわれることが特徴ですが、小さい子どもにもよくある行動と区別がつきにくいため、就学期以降に診断されることが多いといわれています。また、個人差はありますが、年齢とともに多動性の傾向が落ち着いてくるケースもあります。
ADHDの子どもたちは、「やろうと思っても止められない」ことに本人も戸惑い苦しんでいるため、周囲の理解が求められます。
【ADHDの主な特徴】
- 集中力が続かず、気が散りやすい
- 忘れ物やミスが多い
- 思いつくままに行動してしまう
- おしゃべりが止まらない、じっとしていられない
LD(学習障害)
LD(学習障害)は、読む・書く・計算するなどの学習の一部に困難さがあらわれます。知的発達には問題がないにもかかわらず、特定の学習活動だけがうまくいかず、「努力不足」「やる気がない」と誤解されてしまうこともあります。
LDには、大きく分けて次の3つのタイプがあります。
- 「読字障害」:文字を読む・読んだ内容を理解するのが難しい
- 「書字障害」:文字を書くことが苦手
- 「算数障害」:数字の理解や計算に困難がある
LDは、就学後に「読み書きがうまくいかない」「算数だけ極端に苦手」などのつまずきから気づかれることが多いですが、就学前に言葉の発達や指先の運動(微細運動)の苦手さなどから兆候が見えることもあります。
「何度教えてもできない」「他の教科はできるのに」と感じたときは、本人に合った学び方や支援を取り入れることで、力を発揮できる可能性が十分にあります。
【LDの主な特徴】
- 文字を読む・書くのが極端に苦手
- 読んだ内容をうまく理解できない
- 数字の概念や計算がわかりにくい
- 音読や板書が苦手
- 他の教科や活動は得意なことも多い
発達障害について相談できる場所
「子どもの発達が気になるけど、どこに相談すればいいのかわからない」
そんなときは、まず身近な窓口に相談してみるのがおすすめです。
たとえば、お住まいの地域にある児童福祉課(福祉窓口)や子育て支援センターでは、お子さんの発達に関する悩みを気軽に相談できます。「診断は出ていないけど気になることがある」という段階でも、遠慮せず話してみて大丈夫です。
また、かかりつけの小児科や、乳幼児健診のときに出会う保健師さんに相談するのも良い方法です。お子さんの成長を日頃から見ている医師や専門職に話すことで、今後どんな支援や受診が必要かのアドバイスをもらえることがあります。
必要があれば、発達専門の医療機関や療育につながる支援を紹介してもらえる場合もありますよ。
【甲斐市で子どもの発達について相談できる場所】
- 家庭児童相談室
- こども家庭センター児童福祉
- 子育て支援センター(「ヤンチャリカ」「こあら」)
- 子育てひろば
- 各種療育施設
発達障害の子どもが受けられる支援
発達障害のあるお子さんには、医療・福祉・教育の3つの分野で支援を受けることができます。困りごとや特性に合わせて、必要なサポートを組み合わせることが大切です。
医療的支援
発達の気になるお子さんは、小児科・児童精神科・発達外来などの医療機関で、診断や定期的なフォローを受けることができます。
また、作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)・臨床心理士など、専門職による支援も行われています。発達の検査やアセスメントを通して、今のお子さんの状態に合ったアドバイスを受けることができます。
福祉的支援
発達に不安があるお子さんは、療育施設で福祉的な支援を受けることもできます。遊びや日常の活動を通して、集団での関わり方や生活スキル、ことばのやりとりなどを身につけていきます。
療育を受けるためには、多くの場合「通所受給者証」が必要です。これは、医師の診断や相談機関の意見書などをもとに、自治体に申請することで取得できます。
【利用できる主な療育サービス】
- 児童発達支援(未就学児対象)
- 放課後等デイサービス(就学児対象)
- 保育所等訪問支援(在園中の子への支援を専門職が園で実施)
教育的支援
学校では、お子さんの特性に合わせて「合理的配慮」が行われます。困りごとをサポートしながら、安心して学校生活を送れるように支援されます。
学校の先生や療育先の支援士、支援コーディネーターと連携を取りながら、“その子本来の力を発揮できる環境”を一緒に考えていくことが大切です。
【主な教育的支援】
- 特別支援学校:知的・身体的な障害が重い場合などに通う学校
- 特別支援学級:少人数でより手厚い支援を受けられるクラス
- 通級指導教室:通常の学級に在籍しながら、必要なときだけ特別な指導を受ける
甲斐市の療育施設「あら川プラス竜王教室」について
「児童発達支援 あら川プラス竜王教室」は、甲斐市の療育施設です。当施設は、児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を提供しています。
当教室の特徴は、子どもの良いところを見つけて認め、たくさん褒める関わり方です。「いいね!」「ナイス!」「ナイストライ!」といった前向きな声かけが飛び交い、教室全体が明るく笑顔にあふれています。
また、職員の多くは「先生」としてだけでなく「母親」という立場でもあることを活かし、保護者の気持ちに寄り添った支援を大切にしています。
詳しいコース案内と1日のスケジュールはこちらをご覧ください!
まとめ:発達障害かな?と思ったらまずは相談してみよう!
発達障害にはさまざまな種類があり、特性も支援の方法も、子ども一人ひとり異なります。
子どもの発達のことで不安になったり迷ったりするのは、お子さんを大切に思っている証拠です。だからこそ、ひとりで抱え込まず、まずは誰かに相談してみてください。
あら川プラス竜王教室では、ママたちのそんな気持ちに寄り添いながら、子どもたちの可能性を一緒に育てていきたいと考えています。
見学・体験利用も可能です。お子さまの発達や育ちに少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽に
公式LINEか電話080-3389-7680までご連絡ください。
インスタグラムでは活動の様子を投稿していますので、ぜひご覧ください。