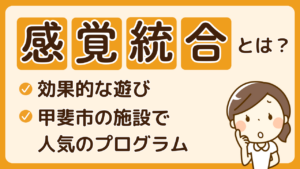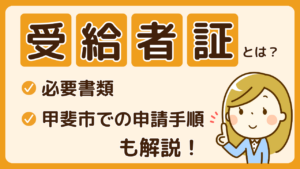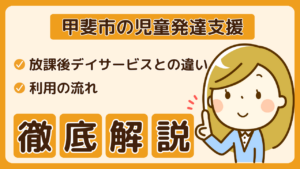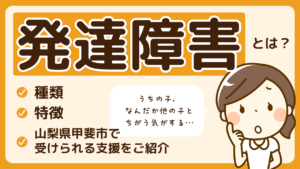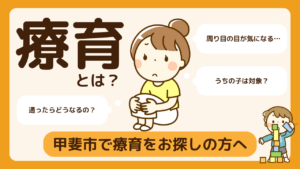ADHD(注意欠如多動症)とは?特徴と診断・治療法について解説

「忘れ物や失くし物が多いのはどうして?」
「家でも学校でもじっとしていられない…もしかしてADHD(注意欠如多動症)?」
そんな不安や疑問をお持ちの方へ。
つい他のお子さんと比べてしまったり、注意しても変わらない姿に戸惑ったり、一人で悩みを抱え込んでいるママも多いのではないでしょうか。ADHD(注意欠如多動症)は性格やしつけの問題ではなく、“脳の働き方による特性”です。
この記事では、発達の専門家がADHD(注意欠如多動症)についてわかりやすく解説します。ADHD(注意欠如多動症)の3つのタイプと診断・治療法についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事が、ママやパパがお子さんを理解し、前向きに向き合うためのヒントになれば嬉しいです!
ADHD(注意欠如多動症)とは
ADHD(注意欠如多動症)とは、生まれつきの脳の働き方に特徴が見られる「発達障害」のひとつです。 ADHD(注意欠如多動症)には、「不注意」「多動性」「衝動性」 の3つの特徴があります。
ADHD(注意欠如多動症)のお子さんは、まわりから「だらしない」「落ち着きがない」「乱暴」と誤解されてしまうこともあります。しかし、これらは脳の特性によるものであり、努力やしつけで変えられるものではありません。
発達障害について知りたい方はこちらをご覧ください。
ADHD(注意欠如多動症)の3つのタイプと特徴
ADHD(注意欠如多動症)は、主な症状の現れ方によって以下の3つのタイプに分けられます。
- 不注意優勢タイプ
- 多動・衝動優勢タイプ
- 混合タイプ
ここでは、それぞれの特徴をチェックリストで詳しく紹介します。特性を知っておくと、「どうしてこんな行動をするの?」という疑問が解消され、ママの気持ちも楽になるでしょう。
不注意優勢タイプ
1つ目は「不注意」の特徴が強く現れるタイプです。「不注意」とは、必要なときに注意を向けたり、集中を持続させたりすることが難しい状態を指します。
例えば、学校で授業に集中できずに他のことに気を取られてしまったり、忘れ物が多かったりするケースがよくみられます。一方で、好きなことに対しては夢中になりすぎて、周りの声が聞こえなくなるほど集中してしまう「過集中」の傾向を持つお子さんもいます。
「不注意優勢タイプ」の特徴
- 外からの刺激で注意がそがれやすい
- 時間や約束を守ることが難しい
- 忘れ物や失くし物が多い
- 授業中、集中し続けることが難しい
- 課題や遊びに集中できる時間が短い
- 話しかけられても聞いていないように見える
- 作業の手順を考えたり、順序立てて行うのが苦手
多動・衝動優勢タイプ
2つ目のタイプは、じっとしていられない、思いついたことをすぐに行動に移してしまうなど、行動や感情のコントロールが難しい状態がみられます。
授業中でも立ち歩いてしまったり、質問の途中で答えてしまったりと、集団生活の中で“落ち着きのなさ”として指摘されることが多いタイプです。
「多動・衝動優勢タイプ」の特徴
- 何の前触れもなく走りだしたり、突然道路に飛び出したりする
- 椅子に座っていても手足を動かしたり、体をゆらすなどそわそわしている
- 座っていなければならない場面でも、立ち歩いてしまう
- 静かに遊ぶことが難しい
- 落ち着きがなく、まるでエンジンがついているように動き続ける
- おしゃべりが止まらない
- 質問が終わる前に答えてしまう
- 順番を待つのが苦手
- お友達に手を出したり、邪魔をしてしまうことがある
- 感情的になりやすく、興奮しやすい
混合タイプ
3つ目は、「不注意」と「多動性・衝動性」の両方の特徴が見られるタイプです。
ADHD(注意欠如多動症)の中では、混合タイプが最も多いとされています。
ADHD(注意欠如多動症)の診断
ここでは、ADHD(注意欠如多動症)の診断基準と診断が下りる年齢について解説します。
診断はラベルを貼るためのものではなく、その子がよりよく過ごすためのサポート方法を見つける第一歩。診断を受けるべきか迷ったときは、まずはかかりつけの小児科や地域の子育て支援センターなどに気軽に相談してみましょう。
ADHD(注意欠如多動症)の診断基準
診断の際には、アメリカ精神医学会が定めた『DSM-5』(精神疾患の診断・統計マニュアル第5版)の基準が用いられます。
『DSM-5』では、「不注意」と「多動・衝動」のそれぞれに9つの症状が挙げられており、どのくらいの期間・どの場面で症状が見られるかを診断基準とします。
『DSM-5』におけるADHD(注意欠如多動症)の診断基準
- 「不注意」「多動・衝動」の症状が6つ以上あてはまる
- 症状が6か月以上続いている
- 同じ年齢の子どもと比べて行動の特徴が著しい
- 12歳になる前から症状がみられている
- 2つ以上の環境(家庭、学校、その他の活動中など)で症状がみられる
- 症状により学習や生活に支障をきたしている
詳しくは『DSM-5』公式サイトをご覧ください。
ADHD(注意欠如多動症)の診断と年齢
ADHD(注意欠如多動症)は、8歳〜10歳頃に診断されるケースが多いといわれています。4歳頃までは、誰にでも「落ち着きがない」「気が散りやすい」といった傾向が見られるため、発達の個人差か特性によるものなのかを見極めるのが難しいのです。
「もしかしてADHD(注意欠如多動症)かも?」と保護者が気づくタイミングとしても、小学校入学後が多くなります。授業や集団行動が始まり周囲の子どもたちが徐々に落ち着いていく中、ADHD(注意欠如多動症)の特徴が目立ちやすくなるからです。
ADHD(注意欠如多動症)の治療法
ADHD(注意欠如多動症)の治療は、症状をなくすことではなく、お子さんが過ごしやすい状態や環境を整えることを目的としています。
ここでは、ADHD(注意欠如多動症)の治療として、療育と薬物療法の2つをご紹介します。
療育
療育では、ADHD(注意欠如多動症)のお子さんが日常生活や集団生活を送りやすくなるように、環境づくりとスキルの習得をサポートします。
また、保護者に向けて、ADHD(注意欠如多動症)の子どもへの適切な関わり方が学べるプログラムもあります。子どもの行動の背景を理解し関わり方を工夫することで、親子双方のストレスが減り、家庭の雰囲気も安定していきます。
薬物療法
薬による治療では、脳内の神経伝達物質(ドーパミン・ノルアドレナリンなど)の働きを整えることで、注意力や衝動のコントロールをサポートします。
近年の研究で、ADHD(注意欠如多動症)には脳の前方にある「前頭前野」などの神経ネットワークが関係しており、神経信号を伝える物質のバランスが崩れていることが分かってきました。薬物療法はこの働きを助け、集中しやすく、気持ちを落ち着けやすい状態をつくります。
なお、薬の種類や効果の現れ方、副作用には個人差があります。主治医と相談しながら、お子さんに合った方法を一緒に見つけていってください。また、薬だけに頼るのではなく、療育やその他の環境づくりと組み合わせることも大切です。
まとめ:ADHD(注意欠如多動症)かな?と思ったら、まずは相談してみよう!
ADHD(注意欠如多動症)は発達障害のひとつであり、「不注意優勢タイプ」「多動・衝動優勢タイプ」「混合タイプ」の3つに分けられます。少なくとも12歳以前に症状がみられ、小学校入学後に診断されるケースが多くあります。
ADHD(注意欠如多動症)は、性格やしつけの問題ではなく、脳の働き方の特性によるものです。特性を理解して環境を整えることで、お子さんが安心して過ごせるようになり、自己肯定感もアップします。
甲斐市の療育施設「あら川プラス竜王教室」では、お子さんの発達に関するご相談を随時受付中です。お子さんの支援はもちろん、ママたちの気持ちに寄り添い、安心できる居場所でありたいとも考えていますので、お子さんの発達で少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽に公式LINEか電話080-3389-7680までご連絡ください。
また、インスタグラムでは日々の活動の様子を投稿しています。ぜひご覧ください!