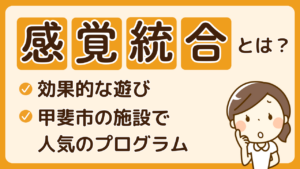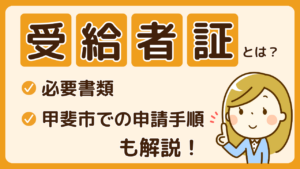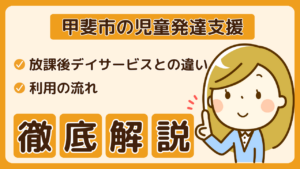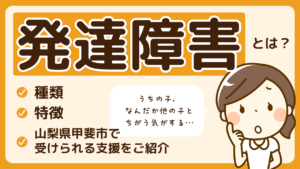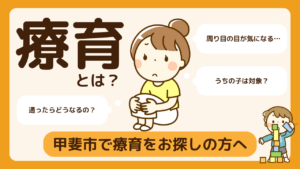ASD(自閉スペクトラム症)とは?年齢別の特徴と関わり方をご紹介!

「うちの子、こだわりが強いけどASD(自閉スペクトラム)なのかな…」
「ASD(自閉スペクトラム)の子どもとどう関わればいいのかわからない…」
そんなふうに、お子さんの発達や日々の関わり方で悩んでいませんか?
周りの子と比べたり、ネットの情報を調べれば調べるほど、不安や迷いが大きくなってしまいますよね。
この記事では、発達の専門家がASD(自閉スペクトラム症)についてわかりやすく解説します。年齢ごとの特徴や関わり方のコツもご紹介するので、お子さんの成長段階にあわせて参考にしてみてください。
この記事が、ママやパパがお子さんを理解し、前向きに向き合うためのヒントになれば嬉しいです!
ASD(自閉スペクトラム症)とは?
ASD(自閉スペクトラム症)とは、生まれつきの脳機能に偏りが見られる「発達障害」の1つです。決して親の育て方が悪いわけではありません。
ASD(自閉スペクトラム症)の特性が正しく理解されないと、「自分勝手」「わがまま」「性格の問題」と受け止められてしまいがちです。実際には、それぞれのお子さんの「脳の特性」によるものなので、努力やしつけで変えられるものではありません。
大切なのは「どう工夫すれば過ごしやすくなるか」という視点です。周囲が特性を理解しサポートしていくことで、ASD(自閉スペクトラム症)子どもたちは自分らしく、自己肯定感を育みながら成長していけます。
発達障害について知りたい方はこちらをご覧ください。
ASD(自閉スペクトラム症)の主な特徴
ASD(自閉スペクトラム症)の主な特徴は、大きく分けて 「対人関係や社会的なやり取りが苦手」「こだわりが強い」「感覚に過敏さや鈍さがある」 の3つです。
特性を知っておくと、「どうしてこんな行動をするの?」という疑問が解消され、ママの気持ちも楽になるでしょう。
対人関係や社会的なやり取りが苦手
ASD(自閉スペクトラム症)でよく見られる特徴が、コミュニケーションの難しさです。
周囲からは「空気が読めない」「自分勝手」と誤解されてしまうこともあるでしょう。
- 場の空気や暗黙のルールを読み取るのが苦手
- 比喩や皮肉を理解するのが難しい
- 言われたことをそのままの意味で受け取ってしまう
- 相手の気持ちや考えを想像することが難しい
こだわりが強い
「いつも同じルートで帰りたがる」「このやり方じゃないとダメ」という強いこだわりもASD(自閉スペクトラム症)の特徴です。一見、頑固に見える行動も、本人にとっては安心につながる大切なマイルールなのです。
- 物の配置や順番、勝敗へ強くこだわる
- 自分のやり方に固執する
- 数字や特定のキャラクターなどに強い興味を示す
- 同じ遊びや行動を繰り返す
感覚過敏・鈍さがある
ASD(自閉スペクトラム症)の3つ目の特徴は、感覚の偏りです。定型発達のお子さんにとっては何ともない刺激でも、強い痛みや不快感につながります。逆に、感覚が鈍いというケースもあります。
- 音や光に敏感
- 洋服のタグや靴下の縫い目を極端に嫌がる
- 痛みや暑さ・寒さを感じにくい
年齢別に見るASD(自閉スペクトラム症)の特徴と関わり方
ASD(自閉スペクトラム症)の特徴は成長にともない変化します。ここでは年齢ごとによく見られる特徴と関わり方のコツをチェックリストにまとめました。
ただし、ここに挙げた特徴があるからといって、必ずASD(自閉スペクトラム症)であるというわけではありません。診断は、専門医がさまざまな側面から総合的に判断するものです。あくまで関わり方のヒントとしてご覧ください。
乳幼児期(0〜2歳頃)
赤ちゃんの頃から「育てにくさ」を感じるママがいる一方で、「手がかからない子」として気づかれにくいことも。1歳半健診で初めて発達の遅れを指摘されるケースも少なくありません。ただし、この時期は発達の個人差が大きく、判断が難しいのも事実です。
特徴
- 視線が合いにくい
- 抱っこを嫌がる
- ミルクを飲むのを嫌がる
- あやしても笑わない
- お腹が空いていたりおむつが汚れていたりしても泣かない
- 名前を呼んでも反応しない
- 寝つきが悪い/すぐ目を覚ます
- 後追いをしない
- 発語がない/遅い
- オウム返し(相手が言ったことをそのまま真似する)が多い
- 共同注意(興味あるものを指す、周囲が指さしたものを見る)が見られない
- ドライヤーや掃除機など特定の音に強く反応して不機嫌になる
- 特定の感覚に執着する
- 手をひらひらさせる、体を前後にゆするなど同じ動きを繰り返す
- 偏食(特定の食べ物しか口にしない)がひどい
関わり方のコツ
- 名前を呼んでも反応が薄いときは、視界に入ってから声をかける
- 抱っこを嫌がる子には、いろんな抱き方を試す/ママの服の素材を刺激の少ないものに変える
- 音や光に敏感な子には、刺激が少ない環境をつくる
幼児期(3〜5歳頃)
言葉や遊びの幅が広がり、園での集団生活も始まる3、4歳。このタイミングで周りの子との違いが目立ち、特性に気づくパターンが多くみられます。同時に、療育に通い始めたりお友達と過ごしたりする中で、大きく成長する時期でもあります。
特徴
- ごっこ遊びが苦手
- 1人遊びを好む
- 「どうぞ」「ちょうだい」/「ただいま」「おかえり」など役割のある言葉を逆に使ってしまう
- 大人の手をつかんで欲しいもののところへ連れていく(クレーン動作)
- おもちゃの並べ方や順番に強くこだわる
- 数字や文字・キャラクター・天気図などの記号的なものや限定的なテーマにこだわる
- 順序やルールが変わると混乱し、パニックになりやすい
関わり方のコツ
- 絵カードやホワイトボードなど、視覚的なグッズを使う
- 集団生活において、一斉指示ではなく個別に指示を出す
- 見通しを立てて安心させる
- 成功体験を積み重ねられるようにサポートする
児童期(小学生以降)
小学校に入ると、勉強や宿題など自己管理が求められる場面が増え、交友関係も広がります。年齢が上がるにつれて、周囲と同じようにできないことに気づき、自信をなくしてしまうこともあるでしょう。
この時期は、合理的配慮を受けながら小さな成功体験を積み重ねることが大切です。特別支援学校や特別支援級、通級指導教室の利用も選択肢に入れられます。
特徴
- 先生の話を聞きながら板書するのが難しい
- 指示を理解できず、わからなくても援助を求められない
- 相手の気持ちや意図を想像できず、トラブルになることがある
- 「空気が読めない」と言われてしまう場面がある
- 一方的に自分の話を続けてしまう/会話に割り込む
- 自分なりのやり方や手順にこだわり変化を嫌がる
関わり方のコツ
- 本人が学習しやすい教材を使う
- 視覚教材を活用する
- 一緒に相手の気持ちを考える練習をする
- 成功体験を積み重ねられるようにサポートする
まとめ:ASD(自閉スペクトラム症)かな?と思ったら、まずは相談してみよう!
ASD(自閉スペクトラム症)は発達障害の1つで、よくみられる特徴は、「対人関係」「こだわりの強さ」「感覚の偏り」の3つです。特徴の現れ方は年齢やお子さんによって大きく異なります。
お子さんの発達で不安や疑問を感じたときは、ひとりで抱え込まず、まずは専門家に気軽に相談してみましょう!相談先は、園や学校の先生、子育て支援センター、かかりつけの小児科でもOKです。
甲斐市の療育施設「あら川プラス竜王教室」でも、お子さんの発達に関するご相談を受け付けています。
お子さんの支援はもちろん、ママたちの気持ちに寄り添い、安心できる居場所でありたいとも考えていますので、お子さんの発達で少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽に公式LINEか電話080-3389-7680までご連絡ください。
また、インスタグラムでは日々の活動の様子を投稿しています。ぜひご覧ください!