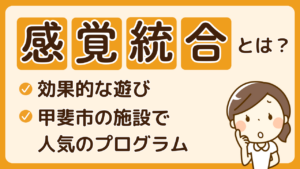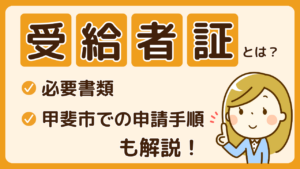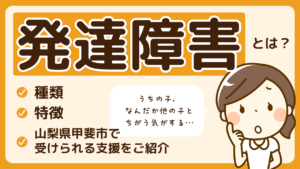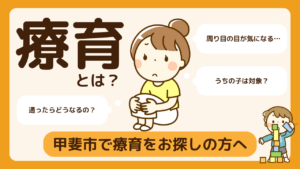【甲斐市の児童発達支援】放デイとの違いや利用の流れを解説!
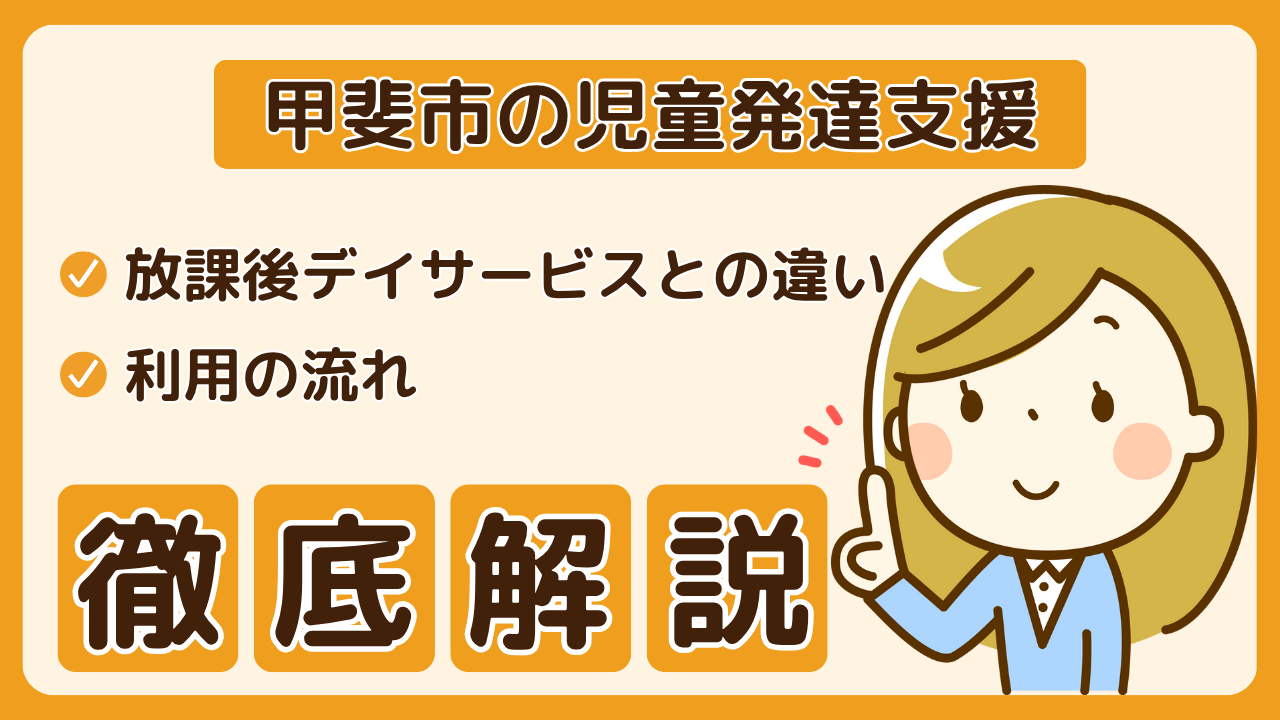
お子さんの発達のために、甲斐市で療育施設をお探しの皆さん、
「児童発達支援って何?放デイとの違いは?」
「児童発達支援の支援内容が知りたい」
そんな疑問をお持ちではないですか?療育について調べ始めたばかりだと、聞きなれない言葉が多く、難しく感じてしまうかもしれませんね。
この記事では、児童発達支援について、放デイとの違いや利用の流れを分かりやすく解説します。また、甲斐市の児童発達支援事業所「あら川プラス竜王教室」の支援内容もご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
児童発達支援とは?
児童発達支援とは?
児童発達支援とは、未就学児(小学校入学前)の障害のあるお子さんや、発達に課題のあるお子さんを対象とした、児童福祉法に基づく通所型のサービスです。
児童発達支援では、お子さん一人ひとりに合わせた「個別指導計画」に基づき、日常生活の基本的なスキルから、コミュニケーション能力や社会性を身につけていきます。また、入園や入学に向けて、スムーズに集団生活へ移行するためのトレーニングも行われます。
さらに、お子さん本人だけでなく、そのご家族へのサポートも、児童発達支援の重要な役割の1つです。
放課後等デイサービス(放デイ)との違い
児童発達支援と放課後等デイサービス(以下、放デイ)には、対象年齢に違いがあります。放デイは小学校入学から高校卒業(6歳〜18歳)のお子さんが対象ですが、児童発達支援は未就学のお子さんが対象です。
放デイは就学児を対象とするため、放課後や土曜日、夏休みなどの長期休暇中に通うのが一般的ですが、児童発達支援は平日の日中にも利用が可能です。
事業所によっては、児童発達支援または放デイのいずれかのサービスを提供しているところもあれば、両方のサービスを取り入れているところもあります。「あら川プラス竜王教室」では、児童発達支援と放デイの両方を提供しています。
児童発達支援の利用方法
児童発達支援を利用するためには、自治体が発行する「受給者証(障害児通所受給者証)」が必要です。
「受給者証」は、「障害者手帳」や医学的な診断書がなくても、医師から療育の必要性を認められていれば発行できます。自治体によって必要書類が異なるため、詳細はお住まいの自治体の福祉窓口に確認しましょう。
なお、「障害児通所受給者証」の継続には、1年に1回の更新が必要です。
甲斐市での「受給者証」取得については、甲斐市公式サイトをご確認ください。
「あら川プラス竜王教室」の利用の流れと料金についてはこちらこちらをご覧下さい!
児童発達支援の内容
「児童発達支援ガイドライン」では、児童発達支援の役割として、以下の3つが定められています。
- 「発達支援(本人支援・移行支援)」
- 「家庭支援」
- 「地域支援」
ここでは、役割別の具体的な支援内容を分かりやすくお伝えします。
発達支援
発達支援は、「本人支援」と「移行支援」の2つに分けられます。それぞれ詳しくみていきましょう。
本人支援
本人支援とは、「障害のあるお子さんが、将来、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにすること」を大きな目標とした支援です。
児童発達支援において、子どもの発達を支える「5領域」が定められており、本人支援では、この「5領域」全てを含めた総合的な支援を提供することが義務付けられています。
「5領域」
- 健康・生活
- 運動・感覚
- 認知・行動
- 言語・コミュニケーション
- 人間関係・社会性
移行支援
移行支援とは、障害のあるお子さんが児童発達支援事業所を卒所してから、保育園や幼稚園、小学校などの集団生活にスムーズに移行できるようにするための支援です。
必要に応じて移行先にお子さんに関する情報を提供し、移行先でもふさわしい支援が受けられるようサポートします。
家族支援
家族支援とは、保護者の方が安心して子育てできるように、心理的・物理的にサポートする支援です。
具体的には、定期的な保護者面談でお子さんの発達状況を共有し、お子さんに必要な支援について一緒に考えます。また、お子さんとの関わり方を学べる、保護者向けのトレーニングが行われることもあります。
地域支援
地域支援では、障害のあるお子さんが地域で適切な支援を受けられるよう、保健・医療・福祉・教育などの機関と連携していきます。
地域の子育て環境を整えることも、児童発達支援の役割の1つなのです。
児童発達支援の目的別プログラム例
児童発達支援のプログラムは、「個別指導計画」に基づき、お子さん一人ひとりに合わせたカリキュラムが組まれます。支援は、集団療育、個別療育、親子療育を組み合わせて実施されます。
さっそく、目的別のプログラム内容をみていきましょう。
ことば
声かけで発語をうながしたり、語彙を増やしたりします。言語聴覚士による専門的な機能訓練が行われることもあります。
コミュニケーション・社会性
集団療育で行われることの多いプログラムです。ソーシャルスキルトレーニング(SST)や自由遊び、ルールのある遊びなどを通して、お友達や周りの人と上手にコミュニケーションをとる方法を学びます。
日常動作のトレーニング
食事・トイレ・着替えなどの基本的な生活習慣の練習をします。折り紙や工作などを通して、指先のトレーニングも行われます。
就学準備プログラム
文字の読み書き、簡単な計算、時計を読むなど、就学・就園に向けた学習と、ソーシャルスキルの習得を行う事業所もあります。
運動プログラム
遊びながら楽しく身体を動かすことで、運動機能の発達をうながします。運動プログラムでは、平均台やトランポリン、ボール投げなど、全身の筋肉を使い体を大きく動かす「粗大運動」が行われます。
親子関係
親子で一緒にプログラムを受け、お子さんへの関わり方を学びます。親子1組だけの場合もあれば、多くの親子が一緒に参加する形式もあります。
児童発達支援事業所のタイプ
児童発達支援事業所には、保育園や幼稚園のように毎日通うタイプや、週に数回だけ通うタイプもあります。
お子さまの必要に応じて、平日は保育園や幼稚園の前後に親子で1時間ほど通い、休日はお子さまだけで半日〜1日通うことも可能です。
事業所のタイプやお子さんのニーズに合わせて柔軟に組み合わせられるので、各事業所に直接問い合わせてみることをおすすめします。
「あら川プラス竜王教室」児童発達支援の1日のスケジュールはこちらをご覧ください!
あら川プラス竜王教室のプログラム
最後に、「あら川プラス竜王教室」で行われているプログラムをご紹介します!
音楽遊び
リトミックを活用し、跳ねる・走る・歩くなどの全身運動を行い、身体能力の向上や集中力、想像力を育みます。また、ピアニカやタンバリン、トライアングルなど身近な楽器を使って、楽しみながら音楽感覚を養います。
学習活動
百玉そろばんを使って数の概念や計算方法を学び、粘土や図形パズル、個別ワークを通じて思考力を育てます。季節ごとの制作活動も行い、創造力を刺激します。
運動遊び
アザラシ体操や柔軟、ブリッジなどで体作りを行い、トランポリンや縄跳び、バランスボールを使って身体を動かします。運動を通じて、順番やルールを守ること、最後まで話を聞くなどの社会性も学べます。
まとめ:児童発達支援でお子さんとご家族をサポートします!
未就学児を対象とした児童発達支援では、お子さんが日常生活や就学のために必要なスキルを身につけるためのサポートが行われます。
さらに、ご家族の方が安心して子育てできるよう、心理的・物理的な支援を行い、就学に向けたサポートをする場でもあります。
あら川プラス竜王教室では、ママたちの気持ちに寄り添いながら、子どもたちの可能性を一緒に育てていきたいと考えています。
見学・体験利用も可能です。お子さまの発達や育ちに少しでも気になることがあれば、どうぞお気軽に公式LINEか電話080-3389-7680までご連絡ください。
インスタグラムでは活動の様子を投稿していますので、ぜひご覧ください。
参考資料:児童発達支援ガイドライン(令和6年7月)